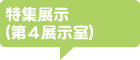
特集展示(第4展示室)
亡(な)き人と暮(く)らす―位牌(いはい)・仏壇(ぶつだん)・手元供養(てもとくよう)の歴史と民俗―
2022年3月15日[火]~2022年9月25日[日]

みなさんは、位牌や仏壇などという言葉を聞いたことがあるでしょうか。自分の家にあるという人もいるかもしれませんね。仏壇は、仏さまとともに亡くなった家族をまつる場でもありました。
今回の展示では、仏壇や位牌、仏具などさまざまな道具に注目し、仏壇がどのようにまつられてきたのか、そこでは地域によるいろいろなあり方や、現代の変化なども含めて、私たちはどのように亡くなった人を考えてきたのかについて、みていくものです。
 |
 |
|
戸棚(とだな)式家具仏壇 青森県で使われていたもので、家具として置くことができる仏壇で、あまり飾りはついていません。 |
トートーメー 国立歴史民俗博物館蔵 沖縄の位牌で、赤い札に先祖の名前を書き、たくさんの先祖を一緒にまつることができます。中国文化の影響を受けた形をしています。 |
 |
 |
|
二代目中村翫雀(かんじゃく)死絵 歌舞伎(かぶき)の役者である中村翫雀が亡くなった時に出された浮世絵です。位牌に戒名(かいみょう 仏教における亡くなった人の名前)といっしょに、手に数珠(じゅず 仏さまを拝むための道具)を持った翫雀の姿が描かれています。 |
遺影(いえい)写真付位牌 まだ写真がめずらしい時代に、亡くなった人の写真と、戒名を書いた位牌が合体したものです。 |
 |
 |
|
地蔵(じぞう)の土人形 国立歴史民俗博物館蔵 秋田市八橋で作られた地蔵の土人形です。子どもが亡くなると、名前や亡くなった日を裏に書いて、お寺に置き、安らかであることを祈ります。 |
モリモノ 個人蔵 これは食べ物を表すかざりものです。埼玉県の東の方の地域では、8月のお盆のときに蓮の花の造花と一緒にこれを飾って、いつも仏壇に花と食べ物が供えられているようにしています。 |
- 名 称
- 亡き人と暮らす―位牌(いはい)・仏壇(ぶつだん)・手元供養(てもとくよう)の歴史と民俗―
- 会 場
- 第4展示室 特集展示室
- 会 期
- 2022年3月15日[火]~2022年9月25日[日]
- 開館時間
- 9:30~17:00(入館は16:30まで)
- 休館日
- 月曜 (休日の場合は次の日)、6月7日(火)、8月2日(火)、9月13日(火)
※5月2日(月)・8月15日(月)は開館 - 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー