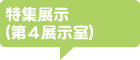
特集展示(第4展示室)
柳田國男(やなぎだくにお)と考古学(こうこがく)
―柳田考古遺物(いぶつ)コレクションからわかること―
2016年4月12日[火]~2016年10月10日[月・祝]

みなさんは、柳田國男という人を知っていますか?
日本民俗学(みんぞくがく)の父と言われた人で、明治から昭和にかけて活躍(かつやく)した人です。
民俗学とは、人々の話を聞き、生活を観察(かんさつ)することで、私たち自身の生活や文化の変化してきた様子を研究する学問です。
これに対し、考古学とは、地面の中から出てきたもの(遺物)から昔の人々の生活や文化を研究する学問です。
この展示では、柳田國男が持っていた考古資料から、考古学や民俗学といった学問が、どのような方法で、何のために歴史を明らかにしようとしてきたのかを考えていきます。

|
柳田國男(明治41年ころ) 当時農商務省につとめていました。(成城大学民俗学研究所所蔵) |

|
「柳田」と書かれた名刺(めいし)箱に入っていた石器や貝の化石 (国立歴史民俗博物館蔵) |

|
柳田國男『明治三十九年樺太(からふと)紀行』に出てくる「ソロイヨフカ」の注記がある石斧(せきふ)です。(国立歴史民俗博物館蔵) |

|
柳田國男が北海道・サハリン旅行の際に収集したかと思われるオホーツク文化の土器の破片です。(国立歴史民俗博物館蔵) |
- 名 称
- 柳田國男(やなぎだくにお)と考古学(こうこがく)
―柳田考古遺物(いぶつ)コレクションからわかること― - 会 場
- 第4展示室副室
- 会 期
- 2016年4月12日[火]~2016年10月10日[月・祝]
- 開館時間
- ~9月:9時30分~17時00分 (入館は16時30分まで)
10月~:9時30分~16時30分 (入館は16時00分まで) - 休館日
- 月曜 (休日の場合は次の日) ※5月2日、8月15日は開館
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー