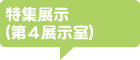
特集展示(第4展示室)
中国・四国地方の荒神信仰(こうじんしんこう)
-いざなぎ流・比婆荒神神楽(ひばこうじんかぐら)
2014年7月23日[水]~2015年1月12日[月・祝]

昔の人たちは「ていねいにおまつりしないと、災い(わざわい)をもってくる神がいる。けれども、ていねいにまつれば、家や村を守ってくれる。」と信じていました。荒神(こうじん)も、そういう神のひとつです。人々は、自分たちのくらしをよくするために、こういう神にいのりをささげ、まつってきました。
この展示では、今でも中国・四国地方に残っているこの荒神信仰(こうじんしんこう)を、いろいろなものを通してみていきます。
 |
 |
|
|
何年かに1度、村の人たちがあつまって神楽(かぐら)という祈りをします。この面は、荒神のすがたになる人がかぶる面です。これをかぶって舞いながら、幸せを願います。 |
神楽(かぐら)を荒神にささげるためのぶたいです。 ぶたいにつるされた竜(タツ)は、ぶたいの前の田んぼからとった稲のわらでつくられています。(この神楽を写した映像は、第4展示室のこのぶたい左にある画面で見られます。) |
 |
||
|
紙を切ってつくった御幣(ごへい)というものです。女辰(めんたつ)とよばれる女性の水神を表現したものです。これに祈って、水に感謝をささげて、病気をなおしたりくらしがうまくいったりするようにと願いました。 |
- 名 称
- 中国・四国地方の荒神信仰(こうじんしんこう)-いざなぎ流・比婆荒神神楽(ひばこうじんかぐら)
- 会 場
- 第4展示室(近世)副室
- 会 期
- 2014年7月23日[水]~2015年1月12日[月・祝]
- 開館時間
- ~9月:9時30分~17時00分 (入館は16時30分まで)
10月~:9時30分~16時30分 (入館は16時00分まで) - 休館日
- 月曜 (休日の場合は次の日)
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー