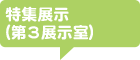
特集展示(第3展示室)
描かれた寺社境内(じしゃけいだい)
2019年12月24日[火]~2020年2月2日[日]

江戸時代後期になると、人びとの旅や行楽への関心が強まり、各地の名所に関するさまざまな画像が大量に制作されました。
多くの参拝客を集める寺社が制作に関わった一枚刷りの境内図も多数残っています。参拝客は実際にそれを手にとって境内や周辺の名所を巡るとともに、旅の土産としても持ち帰ったのでしょう。
今回の展示では、こうした江戸時代中・後期に描かれた、空から見下ろしたような寺社の境内図を絵画や版画を通してご覧ください。
 |
| 松川龍椿(りょうちん) 京都名所図屏風(左隻) 江戸時代末期 金閣寺、北野天満宮、嵐山などが描かれている。 |
 |
諸国名所図手鑑(てかがみ) 江戸時代中期 京都を中心に住吉大社(すみよしたいしゃ)や厳島神社(いつくしまじんじゃ)など諸国の有名な寺社の境内を描き集めた画帖(がちょう)で、作者は明らかではない。 |
 |
歌川広重 東都名所・芝神明増上寺(しばしんめいぞうじょうじ)全図 天保(1830~44)後期 名所絵の第一人者である歌川広重が描いた3枚続きの江戸名所絵シリーズ中の1図。「江戸名所図会」巻一の挿絵(さしえ)「三縁山(さんえんざん)増上寺」にもとづいて描かれている。 |
- 名 称
- 描かれた寺社境内(じしゃけいだい)
- 会 場
- 第3展示室(近世)特集展示室
- 会 期
- 2019年12月24日[火]~2020年2月2日[日]
- 開館時間
- 9時30分~16時30分 (入館は16時00分まで)
- 休館日
- 毎週月曜日(休日の場合は次の日)
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー