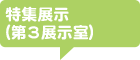
特集展示(第3展示室)
吉祥(きっしょう)のかたち
2019年1月5日[土]~2019年2月11日[月祝]

吉祥(きっしょう)とは、良いきざし、めでたいしるしを意味する言葉です。
みなさんの身近なものから例をあげると、端午の節句の「鯉のぼり」の鯉(こい)は、吉祥に関わりがあります。登竜門(とうりゅうもん)という立身出世(りっしんしゅっせ)にかかわる言葉に表されるように、中国の黄河(こうが)の竜門という急な滝を登った鯉は竜になるという伝説(でんせつ)があります。
このことから、鯉には、子どもが元気に成長し、出世して立派な大人になって欲しいという吉祥の意味(いみ)がこめられているのです。
 |
瀑布鯉魚図(ばくふりぎょず) 楫取魚彦(かとりなひこ)筆 1769(明和6)年 |
上の画像は、今回の展示にある鯉の滝登りの図です。
私たちの生活の中には、この他にも吉祥を表す動植物があり、昔から絵画や工芸品(こうげいひん)に用いられてきました。例えば松竹梅(しょうちくばい)や鶴亀(つるかめ)です。
今回の展示では、歴博所蔵(れきはくしょぞう)の絵画や工芸品(こうげいひん)の中から吉祥に関わるものをよりすぐり、それらにこめられた吉祥の意味を読みといてご紹介します。ぜひごらんください。
 |
梅樹下草模様小袖(ばいじゅしたくさもようこそで) 江戸時代中期~後期 きびしい寒さの中で花を開く梅は、吉祥のシンボルです。その生命力から長寿(ちょうじゅ)と子孫繁栄(しそんはんえい)を表しています。 これは琳派(りんぱ)の絵師、酒井抱一(1761~1828年)がえがいた小袖(和服の元となったもの)で、鳥取藩主(とっとりはんしゅ)の池田家に伝わるものです。 |
 |
龍宮城模様一つ身(りゅうぐうじょうもようひとつみ) 江戸時代後期 浦島太郎(うらしまたろう)の物語にある龍宮城(りゅうぐうじょう)も、永遠(えいえん)や長寿(ちょうじゅ)を意味する吉祥のシンボルです。 |
 |
牡丹獅子置物(ぼたんじしおきもの) 美濃・魁翠園製(かいすいえんせい) 1853(嘉永6)年頃 (国立歴史民俗博物館蔵) 能(のう)の演目(えんもく)「石橋(いしばし)」の場面です。菩薩(ぼさつ)の使いの獅子が石橋の上にあらわれ、美しいボタンの花にたわむれて舞(ま)う長寿を祝うおめでたい場面です。 |
- 名 称
- 吉祥(きっしょう)のかたち
- 会 場
- 第3展示室(近世)副室
- 会 期
- 2019年1月5日[土]~2019年2月11日[月祝]
- 開館時間
- 9時30分~16時30分 (入館は16時00分まで)
- 休館日
- 2019年1月7日[月]・15日[火]・21日[月]・28日[月]・2月4日[月]
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー