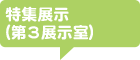
特集展示(第3展示室)
百貨店(ひゃっかてん)と近世の染織(せんしょく)
2016年10月18日[火]~2016年12月18日[日]

今回の特集は、「百貨店と近世の染織」です。百貨店とはデパートのことで、その多くは江戸時代まで着物を売ることに力を入れていました。
明治・大正時代の女性は、ほとんど着物で過ごしていたため、デパートでは女性に着物を買ってもらおうと、「今年の流行」と関係した展覧会を開きました。江戸時代の着物と比較することで、趣味のよさを知らせようとしたわけです。
今回の特集は、大正時代のデパートで開かれた展覧会に出品された、江戸時代の小袖(こそで)などを展示します。友禅染(ゆうぜんぞめ)などの染織の素晴らしい作品を見にきてください。
期間中、展示品の入れかえを行います。
前期 10月18日(火)~11月20日(日)
後期 11月22日(火)~12月18日(日)

|
藤花舟模様帷子(ふじばなふねもようかたびら) (近松門左衛門の二百回忌(き)を記念して)
近松門左衛門がくらした水の都・大阪をイメージして、 舟をししゅうと染(そめ)で表した小袖です。
|

|
幔幕桜楓模様振袖(まんまくさくらかえでもようふりそで) 友禅斎(ゆうぜんさい)謝恩碑(ひ)落成法要 出品
幔幕とは、式場や会場などに張りめぐらす幕のことです。幔幕の細かい模様をよく見てください。白い桜と楓の模様が、幔幕を引き立てています。
|

|
松梅鶴模様振袖(まつうめつるもようふりそで)
赤い地に、飛んでいる鳥を絞り(しぼり)で白く表しています。松や紅梅が描かれ、とてもおめでたい感じがします。 |

|
藤尾長鳥模様振袖(ふじおながどりもようふりそで)
黒地に鹿の子絞り(かのこしぼり)の模様や友禅染(ゆうぜんぞめ)の藤の花に尾長鳥をししゅうで表した、ごうかな振袖です。
|
- 名 称
- 百貨店(ひゃっかてん)と近世の染織(せんしょく)
- 会 場
- 第3展示室(近世)副室
- 会 期
- 2016年10月18日[火]~2016年10月18日[日]
- 開館時間
- 9時30分~16時30分 (入館は16時00分まで)
- 休館日
- 10月24日[月]・31日[月]・11月7日[月]・14日[月]・21日[月]・28日[月]・12月5日[月]・12日[月]
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー