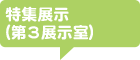
特集展示(第3展示室)
印籠(いんろう)
2015年7月28日[火]~2015年8月30日[日]

「この紋所(もんどころ)が目に入らぬか!」時代劇テレビドラマでおなじみの印ろうです。印ろうは、もとは武士や豊かな町人など男の人が薬を入れて持ち歩く入れ物でしたが、しだいにかざり道具になりました。印ろうの表面には、いろいろな技法(ぎほう)で絵やもようがかかれています。また、印ろうをこしのおびにさげてもち歩く、ひもの先についている根付(ねつけ)にも注目してください。さて、みなさんはどの印ろうを身につけてみたいですか。
 |
 |
|
|
雲龍蒔絵印籠(うんりゅうまきえいんろう)
この印ろうにかかれているのは龍(りゅう)です。表面にうるしで龍のもようをかき、金・銀などの粉(こな)をまきつけてかためた、蒔絵(まきえ)という技法でつくられたものです。根付には鬼(おに)の顔がほられていますね。 |
鴨蒔絵螺鈿象嵌印籠(かもまきえらでんぞうがんいんろう) 銘「観」(めい「かん」)
この印ろうにかかれているのは鴨(かも)です。鴨のかたちの焼きものを、本体の表面にはめこむ象嵌(ぞうがん)の技法(ぎほう)や、貝がらの内側を葉っぱのもように切って、はめこんだりはりつけたりする、螺鈿(らでん)という技法(ぎほう)でつくられています。 |
 |
 |
|
|
花籠蒔絵芝山象嵌印籠(はなかごまきえしばやまぞうがんいんろう)
この印ろうにかかれているのは花籠(はなかご)です。本体の表面をほり、そこに金、銀、象牙(ぞうげ)、貝などをはめこんで花籠のもようを表す、象嵌(ぞうがん)という技法でつくられたものです。 |
こぼれ菊落葉堆朱蒔絵印籠(こぼれきくらくようついしゅまきえいんろう)
このいんろうには赤い菊(きく)がかかれています。この部分は、赤いうるしを厚くぬり重ね、それに菊のもようをほった、堆朱(ついしゅ)という技法でつくられたものです。 |
- 名 称
- 印籠(いんろう)
- 会 場
- 第3展示室(近世)副室
- 会 期
- 2015年7月28日[火]~2015年8月30日[日]
- 開館時間
- 9時30分~17時00分 (入館は16時30分まで)
- 休館日
- 8月3日[月]・17日[月]・24日[月]・31日[月]
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー