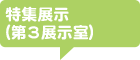
特集展示
-第3展示室-
海を渡った漆器(しっき)II-江戸時代の輸出漆器(ゆしゅつしっき)-
2013年10月29日[火]~2013年12月1日[日]

みなさんが家で食事をするときにみそ汁(しる)を入れる椀(わん)は、何でできていますか。プラスチック製の椀(わん)の家もあると思いますが、木でできた黒や赤の椀(わん)を使っている家もあるでしょう。みそ汁を入れる椀(わん)のように、木でつくった道具にうるしをぬったものを漆器(しっき)といいます。うるしの木の幹(みき)に傷(きず)をつけると木のじゅ液が出てきます。これを木でつくった道具にぬります。うるしをぬると、その道具が水に強くなり長く使いつづけることができるようになります。
日本では、縄文(じょうもん)時代から身の回りの日用品に漆器を使っていました。日本の漆器はじょうぶでデザインもすぐれていることが、16世紀にはヨーロッパに知られるようになりました。そこで、江戸時代には日本からたくさん輸出されるようになりました。
今回の特集展示では、江戸時代に日本でつくられヨーロッパに輸出されたいろいろな道具をみることができます。漆に金銀の粉をまいて模様をかいた漆器、貝がらの内側を細かくくだいてはりつけた漆器などがあります。そのころの人たちがどんなものをつくってヨーロッパに輸出していたのかを見てください。
 |
 |
|
|
皿の中央のもようは、オランダのある金持ちな家のしるしなので、この家から注文されて作られたようです。皿のまわりには、東海道の風景をデザインしています。左横には富士山もかかれています。
|
直径50センチもある大きな皿です。うるしの上に金の粉を散らしてボタンの花をかいています。
|
 |
||
|
手前に扉を開いて使うつくえです。もともと日本でつくられた漆器をつかって、ヨーロッパの職人たちが、当時流行のつくえにつくりかえました。
|
- 名 称
- 海を渡った漆器(しっき)II-江戸時代の輸出漆器(ゆしゅつしっき)-
- 会 場
- 第3展示室(近世)副室
- 会 期
- 2013年10月29日[火]~2013年12月1日[日]
- 開館時間
- 9時30分~16時30分 (入館は16時00分まで)
- 休館日
- 11月5日[火]・11日[月]・18日[月]・25日[月]
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー