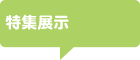
特集展示(第3展示室)
東アジアを駆(か)け抜けた身体(からだ) ―スポーツの近代―
2021年1月26日[火]~2021年3月14日[日]

1932年のロサンゼルス、1936年のベルリンオリンピックに「日本代表」として出場したある台湾人アスリートの競技人生を通し、激動の近代東アジア史、スポーツの近代史を明らかにします。台湾にある国立台湾歴史博物館、国立成功大学といっしょにおこなう展示です。
<本展示のみどころ>
・張星賢(ちょう せいけん)という台湾人アスリートの競技人生に焦点を当てながら、激動の日本と東アジアの近代史を見つめ直します。
・記念1000円硬貨や銅メダル(男子バレーボール)など1964年の東京オリンピック関係資料を展示します。
・ハードル、運動会のプログラムなど、100年前はどのような形や内容だったのか、スポーツから歴史をながめてみます。
・ラジオ体操参加カードはいつからあるのか、はじめて「スポーツ」に出会った人々は、どういう反応をしたのか、野球やラジオ体操の例から考えます。
<プロローグ>
日本にスポーツというものが入ってきてからの約150年間の歴史を、台湾人アスリート、張星賢の生きた道のりを中心にすえて振り返ります。
 |
張星賢スタート写真 |
<第1章 近代史の中のスポーツ>
日本の近代化とともにスポーツという新しい文化がどのように入ってきたのか、人びとの間にどのように定着していったのか、また、そのなかでどのような問題を人々の間に引き起こしていたのか、ということも含めて考えます。
|
|
|
「西洋ウンドヲアソビ」 |
アムステルダムオリンピック女子100m予選の人見絹枝 1928年9月 個人蔵 |
<第2章 帝国日本のスポーツとオリンピック>
1896年、ヨーロッパでは近代オリンピックとして開催されるようになり、日本も参加するようになりました。そのころ日本は日清戦争で台湾を領有した直後でした。
1925年にラジオ放送が開始され、1928年にはラジオ体操が制作されました。
|
|
|
オリンピック大競技双六『少年倶楽部』 |
ラジオ体操参加カードとメダル裏面 1940年代 個人蔵 |
<第3章 世界を駆け抜けた台湾人アスリート 張星賢>
台湾中部の台中で生まれた張星賢(1910~1989)は、日本統治下の台湾で日本語の教育を受け、1931年に早稲田大学競走部に入り、日本でおこなわれていた数々の陸上競技大会に出場しました。
また「日本選手」として2度のオリンピック(ロサンゼルス・ベルリン)に出場しました。いまから90年ほど前のことです。
|
|
|
第10回オリンピック、ロサンゼルス大会参加記念章(表) |
第20回全日本選手権(兼第7回明治神宮体育大会)記念章 1933年10月31日−11月3日 第二十届全日本選手權大會兼第七回明治神宮體育大會(1933) 紀念 国立台湾歴史博物館蔵 |
<第4章 スポーツの戦後>
戦後の復興とスポーツは密接な関係にありました。スポーツの復興がひとびとを元気づけ、戦争により失った自信や喪失感をうめあわせる役目も果たしました。
 |
東京オリンピック開会式男性用ジャケット |
- 名 称
- 東アジアを駆(か)け抜けた身体(からだ) ―スポーツの近代―
- 会 場
- 企画展示室B
- 会 期
- 2021年1月26日[火]~2021年3月14日[日]
- 開館時間
- ~2月:9時30分~16時30分(入館は16時00分まで)
3月~:9時30分~17時00分(入館は16時30分まで) - 休館日
- 月曜 (休日の場合は次の日)
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館、國立臺灣歷史博物館(台湾)、國立成功大學(台湾)

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画








 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー