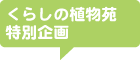
くらしの植物苑特別企画
伝統(でんとう)の朝顔(あさがお) 20年の歩み
2019年7月30日[火]~2019年9月8日[日]
この花を見たことがありますか?

これ、実は朝顔です。今、わたしたちの育てているものとは、だいぶちがいますね。
そもそも朝顔は、奈良(なら)時代に、種が薬として中国大陸から伝わりました。それから何百年もたつうちに、花をきれいにさかせることを楽しむ人がふえました。
江戸時代には何回も朝顔ブームがおこり、たくさんの変わった朝顔が作られました。葉や花の形が変わったものを「変化朝顔(へんかあさがお)」とよび楽しまれていました。
下の写真の花も、どれも変化朝顔です。歴博では、こういう変化朝顔を長らくの間、大切に保存して育ててきました。江戸時代の人が楽しんだ朝顔はどんな花か、ぜひ見にきてください。午前中の早い時間が花の見ごろです!
 |
 |
|
花びらの色と形に注目 名前「青桔梗渦葉短毛青紫糸覆輪桔梗咲八重」 読み方「あお/ききょう/うずば/たんもう/あおむらさき/いとふくりん/ききょうざき/やえ」 |
花や葉の模様に注目 名前「黄斑入蝉葉納戸時雨絞丸咲大輪(蝶々夫人)」 読み方「き/ふいり/せみば/なんど/しぐれしぼり/まるざき/たいりん(ちょうちょうふじん)」 |
|
 |
||
葉やくきに注目 渦小人(うずこびと)と呼ばれ、つるのない朝顔 名前「青渦顰葉渦小人紅筒白丸咲」 読み方「あお/うず/しかみば/うずこびと/べに/つつしろ/まるざき」 |
- 名称
- 伝統(でんとう)の朝顔(あさがお) 20年の歩み
- 開催期間
- 2019年7月30日[火]~2019年9月8日[日]
- 会 場
- 国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑
- 開苑時間
- 9時30分~16時30分(入苑は16時00分まで)
※ただし、8月12日[月]~18日[日]は8時30分から開苑します。
※午前中の早い時間が、花の見ごろです。 - 休苑日
- 毎週月曜日(ただし月曜日が休日の場合は次の日)
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー