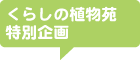
くらしの植物苑特別企画
伝統(でんとう)の朝顔(あさがお)
2017年7月25日[火]~2017年9月10日[日]

夏の花・朝顔、みなさんも育てたことがあると思います。この朝顔、いつごろからわたしたちの身のまわりで咲く花になったのでしょうか。
朝顔は、奈良(なら)時代に中国大陸から薬として伝わりました。それから何百年もたち、江戸時代になると植物を育てる人がふえ、朝顔も多くの人に親しまれる花になりました。
江戸時代に2度の朝顔ブームがおこり、いろいろな朝顔が育てられました。こういう朝顔は、突然、葉や花の形が変わったものなので「変化(へんか)朝顔」とよばれています。
明治時代には、「変化朝顔」とともに大きく咲く朝顔「大輪朝顔」が育てられるようになり、「変化朝顔」よりも「大輪朝顔」を育てる人が多くなったようです。
下の写真は、どれも変化朝顔です。普段、学校やご家庭で育てているものとは、だいぶちがいますね。
歴博では、こういう変化朝顔を保存して育てています。昔の人が楽しんだ朝顔はどんな花か、ぜひ見にきてください。午前中の早い時間が花の見ごろです。
 |
 |
|
葉は糸柳葉(いとやなぎば)と言い、ヤナギの葉に似ていて、さらに糸のように細く、花はナデシコの花のように細い・・・これも朝顔です。 |
花は、花弁の先がとがってキキョウや星の形に似た花です。 |
|
 |
 |
|
花の形が管状で、風鈴に似ています。 |
花の模様に注目してください。 |
- 名称
- 伝統(でんとう)の朝顔(あさがお)
- 開催期間
- 2017年7月25日[火]~2017年9月10日[日]
- 会 場
- 国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑
- 開苑時間
- 9時30分~16時30分(入苑は16時00分まで)
- 休苑日
- 毎週月曜日(ただし月曜日が休日の場合は次の日)
- 主 催
- 国立歴史民俗博物館

 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく スケジュール
スケジュール 企画展示
企画展示 特集展示
特集展示 ファミリープログラム
ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画
くらしの植物苑特別企画


 スケジュール
スケジュール れきはくへ行く前に
れきはくへ行く前に れきはくとは
れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく
家や学校で楽しむれきはく サイトマップ
サイトマップ お問い合わせ
お問い合わせ プライバシーポリシー
プライバシーポリシー